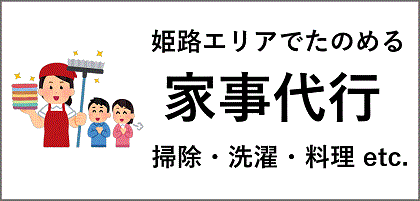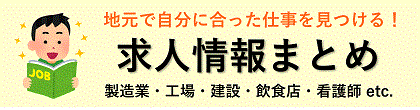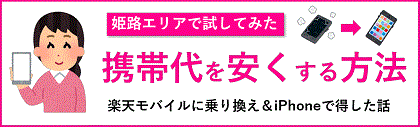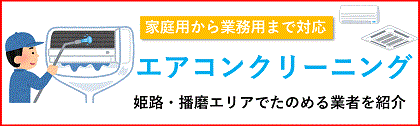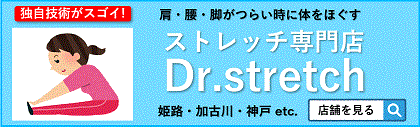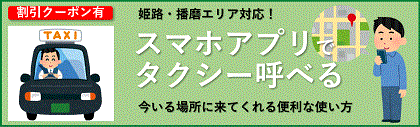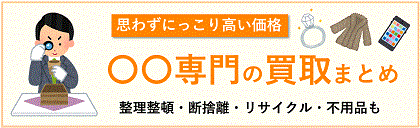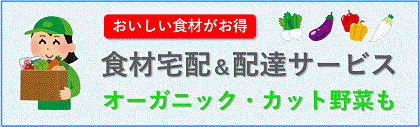明治から戦前にかけて、日本歴史の学者として活躍した、姫路出身の偉人、三上参次先生を紹介します。
三上参次先生は、江戸時代史や日本文学史などの著書を記し、歴史学者として、昭和天皇にご進講した、日本歴史学の権威です。
三上参次先生について、名前を聞いたことがあったけど、家系や生まれ、詳しい功績は知らなかったので、顕彰会の資料を読み解きながら、調べてまとめてみました。
三上参次の生まれと時代背景
三上先生は慶応元年に生まれ、昭和14年に逝去されています。
ということは、慶応元年は1865年なので、明治元年の三年前ということです。
慶応、明治、大正、昭和の時代を生きて、第二次世界大戦の前に逝去されたっていうのは、激動の時代だったのだと思います。
三上先生の生きた時代背景は、3歳の時に明治維新があり、12歳で西南の役、29歳で日清戦争、39歳で日露戦争、49歳で第一次世界大戦、74歳で逝去ということになります。
年齢と出来事を、現代の感覚で見てみると、すごい時代ですね。
平和な世代の感覚からすると、ほんとに激動というか、同世代が戦争で戦ったなんてことが、身近にあるなんて考えられません。
生まれたころは電気・ガス・水道がないのは当然ですし、髪型はちょんまげで和服、コンクリートも鉄骨もない江戸時代末です。
産業においても、何もないところからの近代化です。携帯電話の進化どころではありません。
三上参次と姫路中学 (旧制)
そんな時代を生きた三上先生は、旧制姫路中学(現西高)を経て、農学部を目指し上京。
恩師に文学の道を進められ、20歳で東京大学文学部に入学しました。
正岡子規と夏目漱石が、三上先生の2つ年下なので、同じ時代を東京で過ごしていたのかもしれません。
まさに、坂の上の雲の世界です。
24歳で大学院に進み国史の編纂に携わるようになります。
当時は国としての正史がなく、国史の編纂は明治政府の課題だったようです。
その後、史料編纂事業は、三上先生が中心となり、進められました。
三上参次の進講と昭和天皇
三上参次先生の公職は、東京帝国大学名誉教授、貴族院議員、史学会理事長などを務められ、勲一等旭日大勲章を受章されています。
晩年の三上先生は、昭和天皇への御進講も務めます。
御進講とは、天皇・皇后に講義を行うことで、大正13年から昭和7年の間に延べ24回行われました。
三上先生の御進講は、昭和天皇の教育に大きな影響を及ぼしたとされます。
めちゃめちゃ偉い人です。
文学の夏目漱石が、千円札の肖像になったぐらいですから、国史や明治天皇御紀を編纂した三上先生は、一万円札の顔になってもおかしくないぐらいです。
三上参次と渋沢栄一

また、三上は渋沢栄一との交流もあり、渋沢は『楽翁公伝』(実際の出版は昭和12年〈1937〉、岩波書店)(楽翁=松平定信)を執筆していることになっているが、この書はほぼ三上の指導によっていると思われる。
東京大学 所蔵史料目録データベースより
【追記】三上先生は、新札の肖像画になった渋沢栄一と交流があったようです。お札の肖像画になってもいいぐらいの偉人だと思います。
三上参次の手紙
【参考】明治時代の姫路ガイド『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』のなかで、三上先生の手紙が、前文に記されています。
わが播磨の国には好地誌なし。播磨鑑、播磨志草、播磨名所巡覧図会、などをはじめとし、~中略~、是れ、多くは簡単なる道中案内紀、若しくは好時家の覚え書、ただしは歌枕名寄ともいふべきものにして、まさしく地誌の名を附与し得べきは少し。
『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』前文より
播磨の国には良いガイドブックがない。
他の国には、それぞれの国を紹介した良い本があるが、姫路にもとりあえず作ってほしい、と著者宛に書かれています。
そして明治32年に発行されたのが『沿革考証 沿革考証 姫路名勝誌』です。三上先生のお墨付きです。
『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』は、初版された古書を、現代語で読めるようにした復刻版です。
明治時代の雰囲気を感じながら読むことができます。
姫路の偉人 三上参次
姫路城が国宝に指定された(昭和6年)のも、三上先生のおかげ。
旧制姫路高校(現兵庫県立大学環境人間学部キャンパス)ができたのも、三上先生のおかげ 。
そんな偉い三上先生が、時代とともに忘れ去さられるのはいけません。
最近では、顕彰会が発足するなど、三上先生の偉業をまとめたものが、ネットでダウンロードできるので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
旧制姫路中学校の同窓会「白城会」 三上参次リーフレット
顕彰会のパンフレット(PDF) ダウンロード
※参考文献『現代語訳 沿革考証 姫路名勝誌』